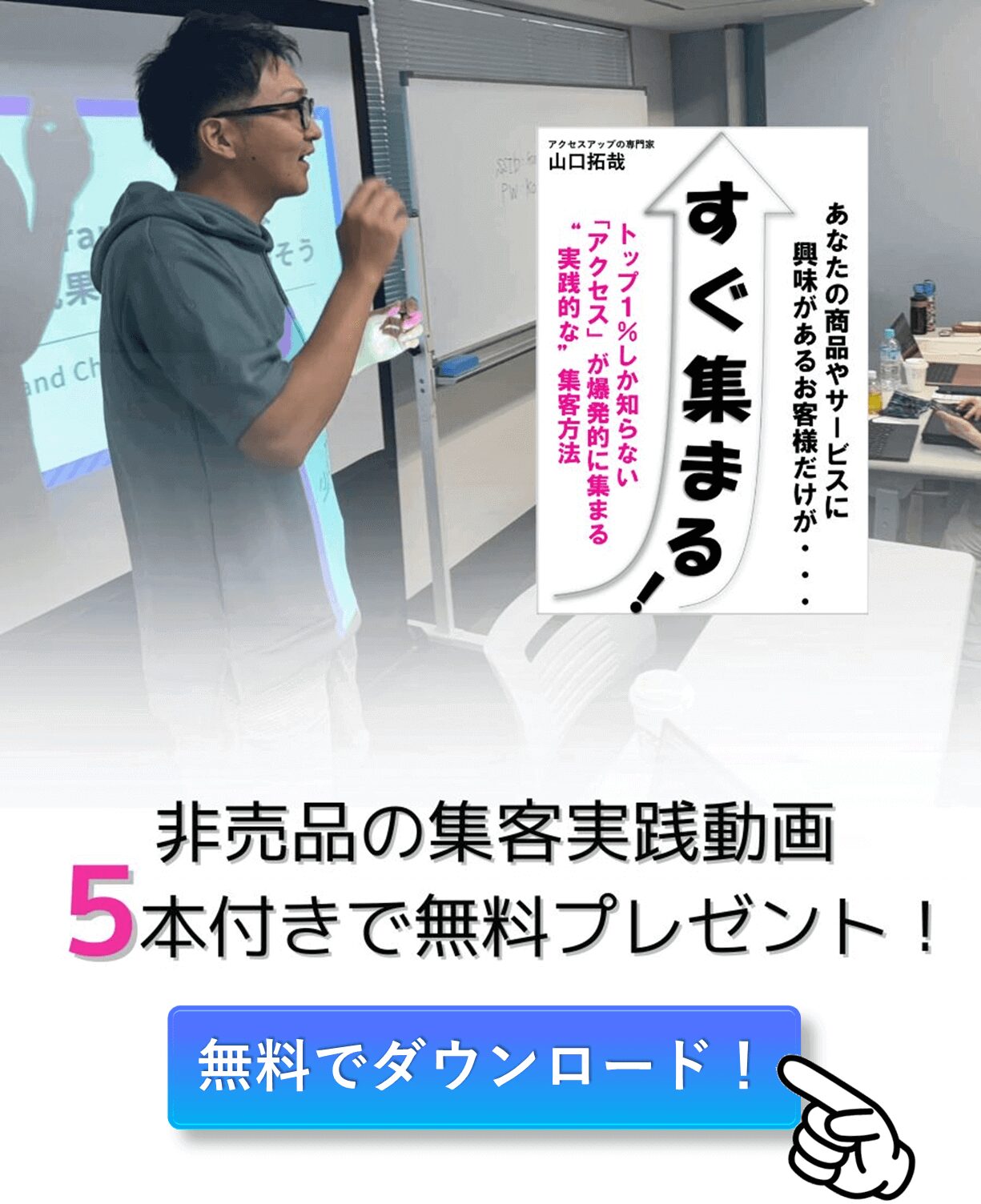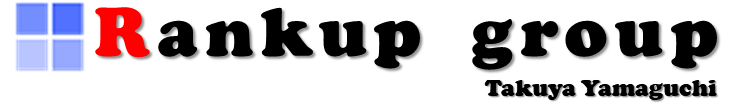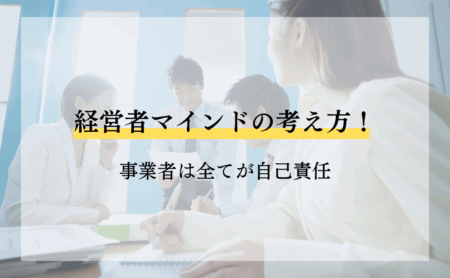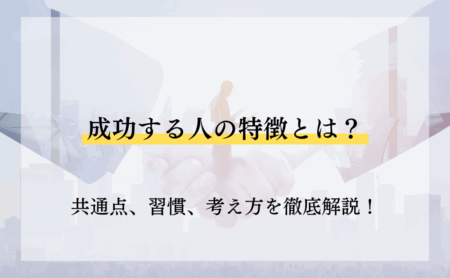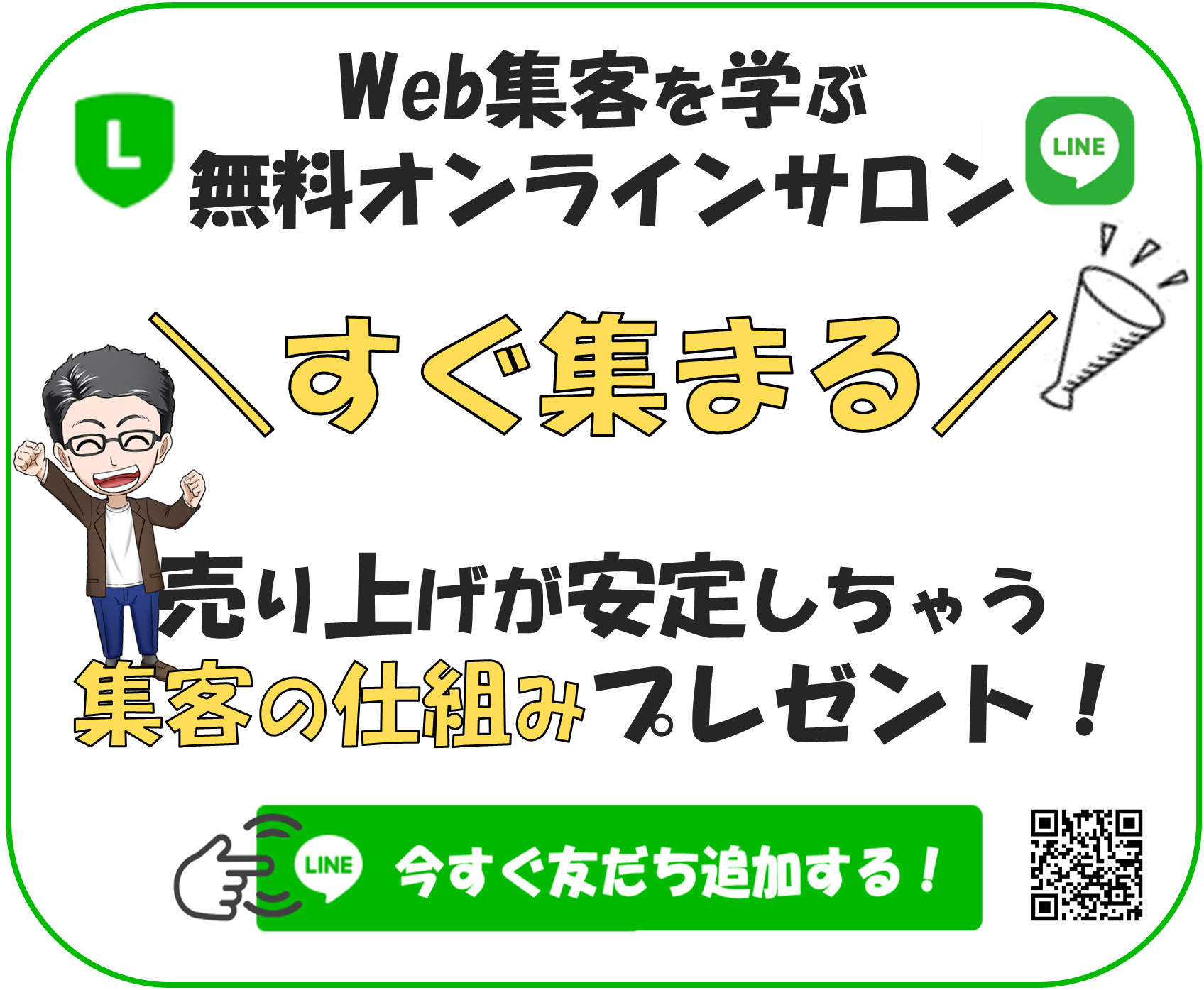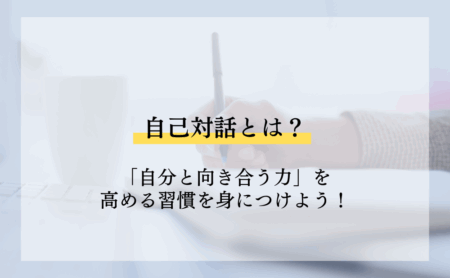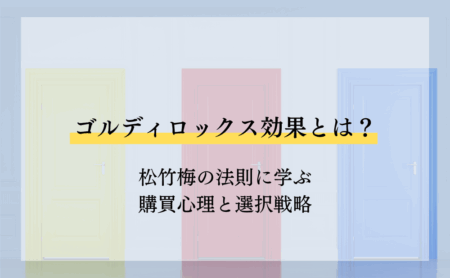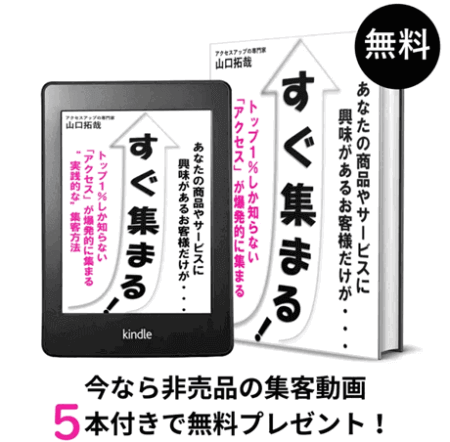経営判断を鈍らせる「現状維持バイアス」とは?企業の成長を妨げる心理と対処法
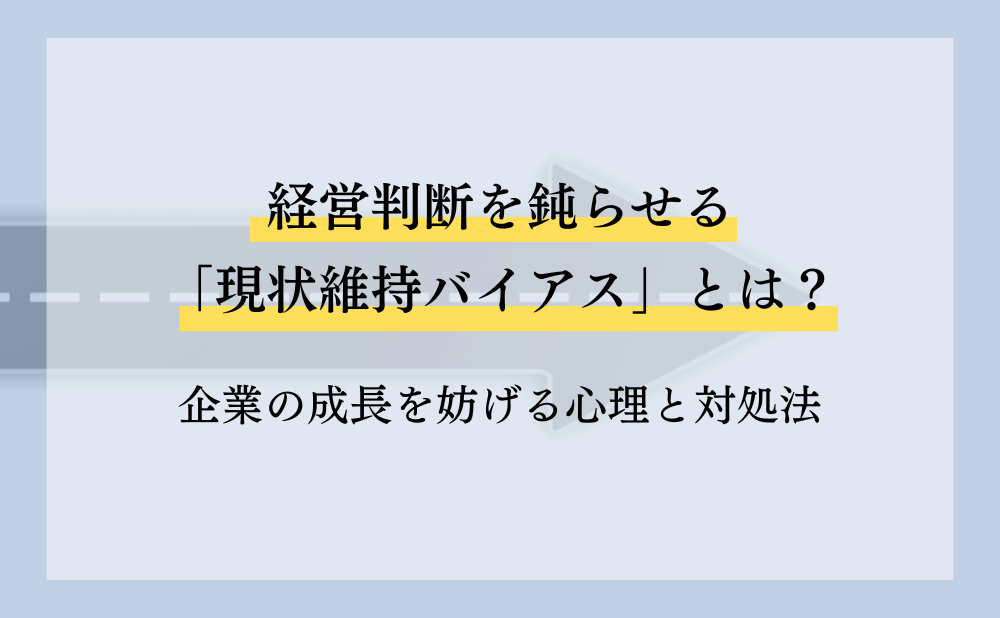
現状維持バイアスは経営判断を鈍らせる人の心理的傾向であり、経営者の頭を悩ませる種です。
現状維持は経営者にとって停滞の危機であり、打破すべき考えです。
当記事では現状維持バイアスを解説しながら、どのように外すのかの方法もお伝えします。
- 現状維持バイアスを知りたい方
- 現状維持バイアスがどのような悪影響を及ぼすのか知りたい方
- 現状維持バイアスの外し方を知りたい方
経営判断を狂わせる「現状維持バイアス」とは?
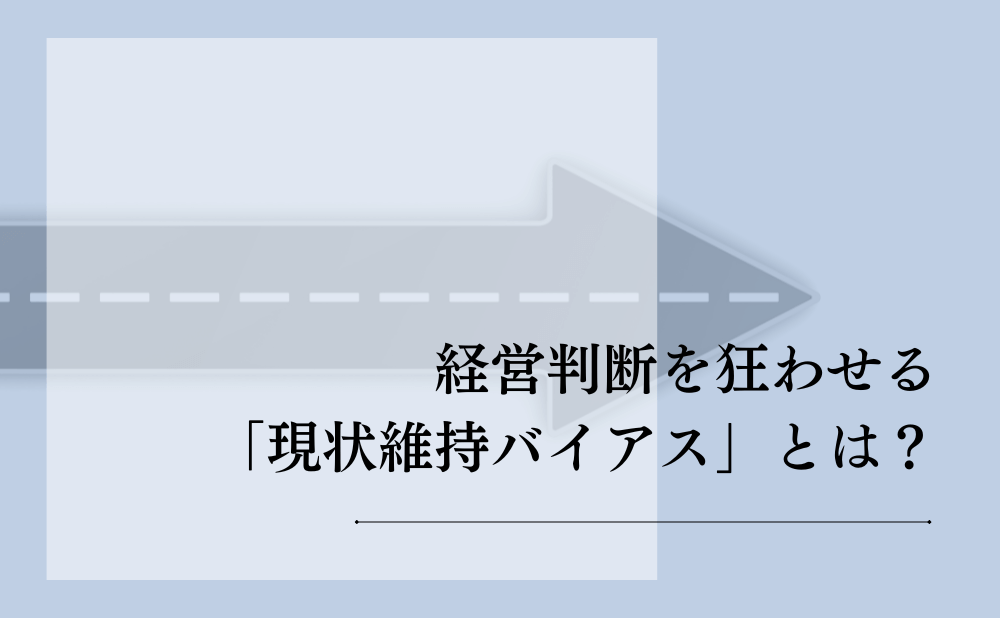
経営判断に重要な現状維持バイアスとはどのようなものなのでしょうか。
以下の項目に沿って解説します。
- 定義と由来
- 経営者はなぜ現状維持に陥りやすいのか?
- 「現状維持=安全」ではない
定義と由来
現状維持バイアスとは、人が新しい選択肢や変化よりも、現在の状況を維持しようとする心理的傾向を指します。
心理学者サミュエルソンとゼックハウザーによって1998年に提唱され、経済学や行動科学の分野において注目されてきました。
現状を変えることには不確実性やコストが伴うため、多くの人が「今のままが最善」と無意識に判断してしまうことで知られています。
ビジネスや経営の現場では、この現状維持バイアスが意思決定を鈍らせたり改革の遅れを招いたりする要因となります。
経営者はなぜ現状維持に陥りやすいのか?
経営者は組織全体に対して責任を負っていて、一つの判断が会社全体の命運を左右する可能性があるため、失敗した際の損失や批判を想像すると、現状を保つほうが心理的に「安全」と感じる傾向があります。
もちろん多くの経営者の方は現状を変えたいと望んでいるのですが、意思決定の際に現状維持バイアスが影響し、「今のままで良い」という判断になってしまうこともあります。
「現状維持=安全」ではない
現状維持は一見すると、波風を立てずに安定を維持する賢明な選択のように思えるかもしれません。
しかし、変化の激しい市場環境やテクノロジーの進化、顧客ニーズの多様化が進んでいる中では、現状を維持すること自体が大きなリスクとなる場合があります。
競合他社が新たな価値を提供し続けている中で、変わらない企業は「選ばれない存在」になってしまう恐れがあり、現状維持は結果的に衰退を招く可能性があります。
「現状から変わりたくない」という思考は、居心地が良い「コンフォートゾーン」から抜け出せない状況と同じです。
コンフォートゾーンから抜け出せないということはリスクなので、何かあったときには変化に対応できるよう事前に準備をしておきましょう。
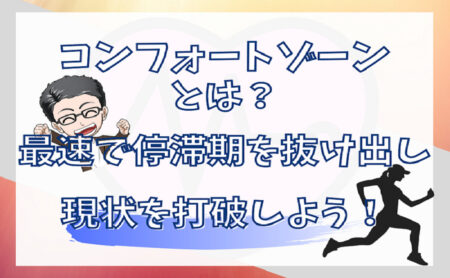
経営での現状維持バイアスの典型例
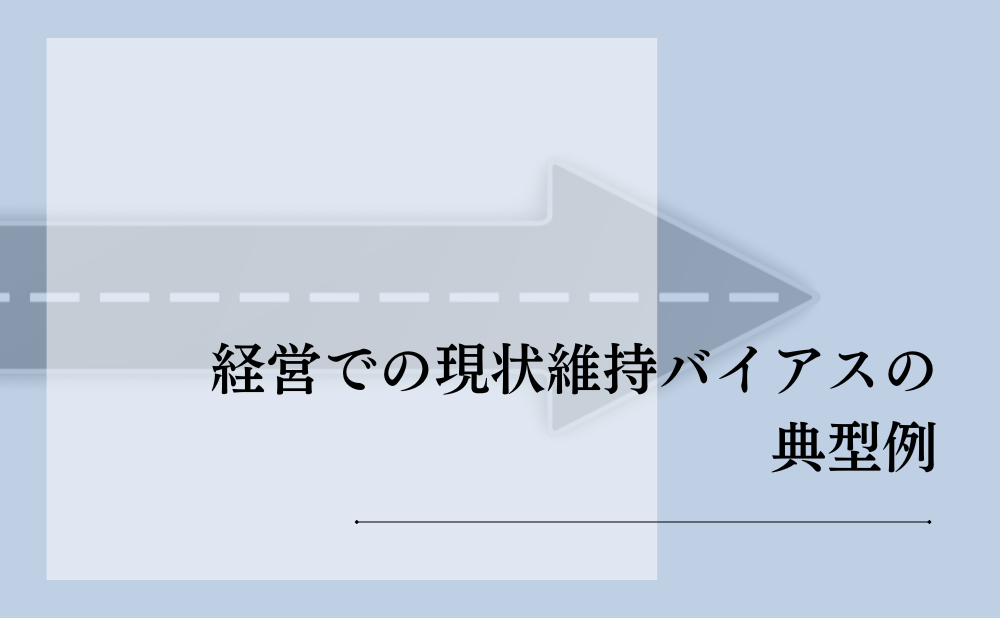
経営における現状維持バイアスが掛かっている典型例として以下のような事例があります。
- 前例の繰り返しばかりになる意思決定
- 市場変化に追いつけず機会を逃す例
- 「変えた方がいい」と分かっていても動けない現場
それぞれ解説します。
前例の繰り返しばかりになる意思決定
前例の繰り返しばかりになる意思決定は、経営での現状維持バイアスの典型例です。
過去の成功体験が柔軟性を失わせ、「これまでこうやってきたから」と新しい方法に挑戦できない空気を生み出しがちです。
結果として、社内や組織に「このままで良い」という考えが根付き、チャレンジ精神を失ってしまいがちになります。
市場変化に追いつけず機会を逃す例
現状維持バイアスで市場変化に追いつけず、機会を逃してしまうことも多いです。
現状維持をしてしまうと、テクノロジーの進化やユーザーのライフスタイルの変化、競合他社の成長など、外部環境が激しく変動していることに気づけないまま取り残される恐れもあります。
たとえば、AIが出現し使い方も分からないまま、活用しなかった企業はWeb業界の中でどんどんシェアを奪われています。
このように外部環境は色々な要因ですぐに変わるため、現状維持ばかりで進むのではなく、新しいことに立ち向かうことも常に行ってください。
「変えた方がいい」と分かっていても動けない現場
改革の必要性を感じていても、実行段階で止まってしまうケースは多くあります。
というのも、変化に伴う業務負荷の増加、社内・組織の反発、不確実性への不安などがあるからです。
特に「業務が回らなくなる」「責任の所在が曖昧になる」といった懸念は、現場の抵抗を強める要因になります。
こういった考えをなくすためには、経営者自身が率先して現場に改革を徹底させ、エラーやミスが出た際には常に修正して前進する姿勢が必要です。
日本人経営者に現状維持バイアスが強く出やすい理由
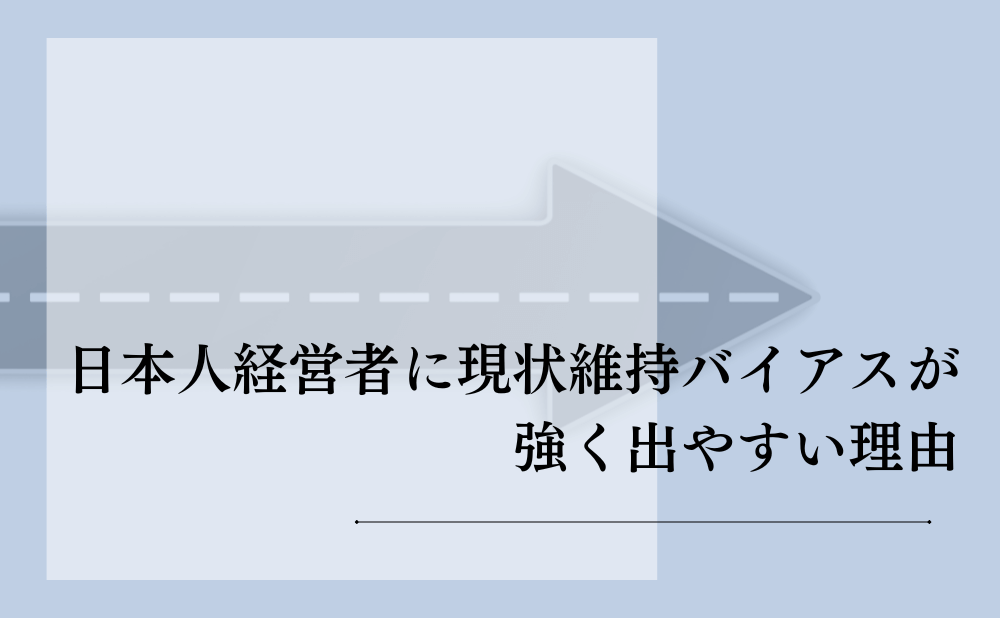
日本人経営者に現状維持バイアスが強く出やすい理由の一例は次のとおりです。
- 同調圧力
- 失敗を過度に恐れる
- 安定志向が強い
それぞれ解説します。
同調圧力
日本社会には「和を乱さない」「空気を読む」ことが美徳とされる文化が根強く存在していて、周囲の意見に逆らうことを無意識に避ける傾向があります。
経営判断においても、社内・組織の多数派や過去の慣例に従うことで摩擦を避けようとする心理が働き、改革を阻む要因になりがちです。
失敗を過度に恐れる
日本では「失敗=評価の低下」という意識が強く、挑戦することよりも失敗しないことが優先されがちです。
経営者も元々企業で働いている方が多く、所属していた企業の風土の悪い面も継承してしまっているかもしれません。
特に「失敗=キャリアがなくなる」という考え方は、事業にとって悪い方向にしか進まない可能性が高いので、「失敗=教訓を得た」という考え方に変えたほうが良いです。
もちろん、事業が立ち行かなくなる失敗はNGなのでリスク管理は行ってください。
安定志向が強い
高度経済成長期や終身雇用制度など、安定を前提とした社会構造が長く続いてきた背景から、日本人の多くは「変わらないこと」に安心を感じやすい傾向があります。
先ほどの例と同じように、元々所属していた企業の悪い風土を継承し、1度成功したらそのまま続けるという考え方をしてしまう方も多いです。
ただ、事業は常に成長を続けなければならないので、会社員時代の考えを変え、常にチャレンジをする精神を持ち続けてください。
現状維持バイアスのメリットとデメリット
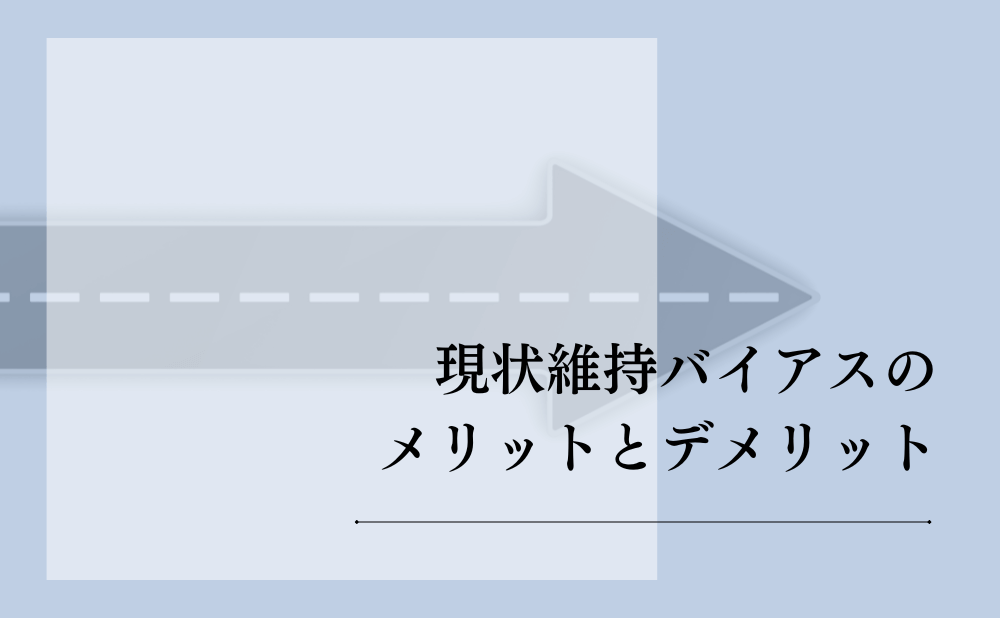
現状維持バイアスのメリットとデメリットについてご紹介します。
- メリット1:リスク回避・信頼維持
- メリット2:心理的な安心感
- デメリット1:成長機会がなくなる
- デメリット2:現状維持は「衰退」につながりやすい
詳しく解説します。
メリット1:リスク回避・信頼維持
今までの方針を続けることで、お客様や取引先からの信頼を維持しやすく、不要なトラブルや混乱を避けることができます。
特に、安定を重視する業界やお客様にとっては、「変わらないこと」自体が価値として評価される場面もあります。
メリット2:心理的な安心感
変化は多くの場合ストレスや不安を与えがちです。
一方、現状維持を選択した場合、従業員や経営陣にとって「今のままでいい」という心理的な安心材料となり、安定した日常業務の継続が可能です。
特に組織文化が保守的な企業・組織では、この安心感が重要な役割を果たします。
デメリット1:成長機会がなくなる
現状に満足し、新たな挑戦を避けるようになると、技術革新(昨今のAI技術など)や顧客ニーズの変化に対応できず、成長の芽を摘んでしまう恐れがあります。
競合が新たな価値を作っている間に、自身の事業が過去の成功体験に縛られたまま停滞し、差を広げられてしまうリスクが高まります。
デメリット2:現状維持は「衰退」につながりやすい
時代の流れや市場環境の変化に対応しないことで、徐々に顧客やパートナーからの信頼を失い、存在感を失っていく可能性があります。
「変わらない」という選択は、「後退」を意味することも多く、知らず知らずのうちに事業全体の競争力を失う恐れがあります。
経営における現状維持バイアスの外し方
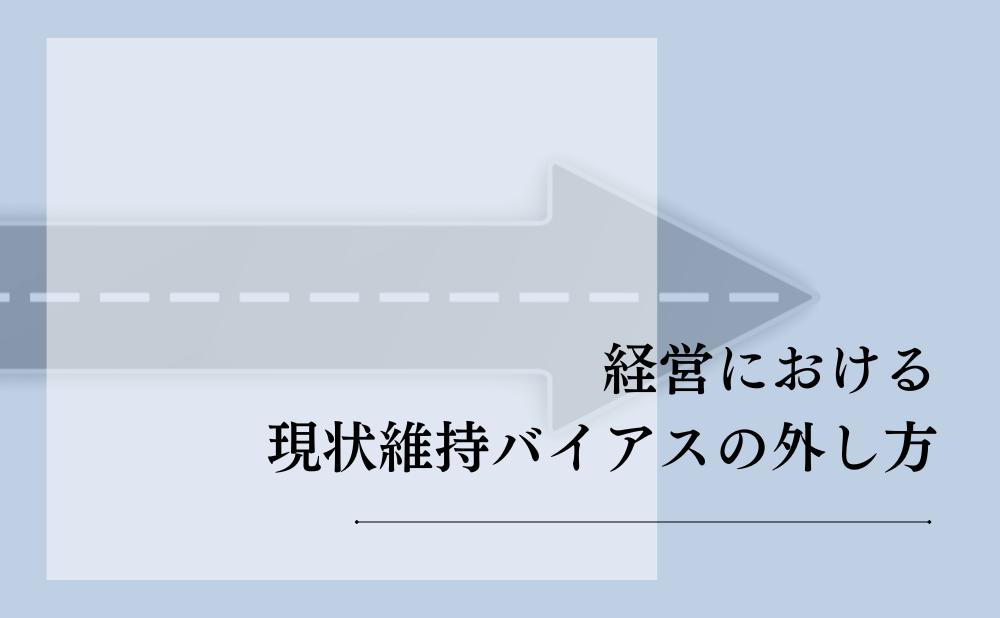
経営における現状維持バイアスの外し方の一例を紹介します。
- 経営者マインドを整える
- データで意思決定を可視化する
- 「失敗のコスト」ではなく「変化しないリスク」で考える
- スモールステップで変化に慣れるマインドセットを作る
それぞれ解説します。
経営者マインドを整える
経営者マインドを整えることは、現状維持バイアスを外す上で最も重要です。
経営者マインドは、一般的な会社員の方とのマインドと異なるため、意識付けをしながら徐々に身につけてください。
データで意思決定を可視化する
勘や過去の成功体験に頼るのではなく、KPIや業績データ、顧客の声など客観的な材料をもとに判断する習慣を身につけましょう。
データに頼らない経営をすると、過去の慣例などに縛られ現状維持バイアスが働きやすくなります。
客観的データをもとにどのような方針で現状を変えていくかを常に意識してください。
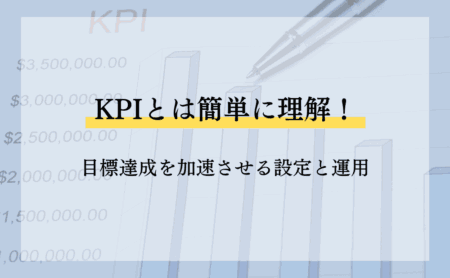
「失敗のコスト」ではなく「変化しないリスク」で考える
変化には当然リスクがありますが、「何もしないこと(現状維持)」自体が最も大きなリスクにもなります。
損失を恐れて停滞するのではなく、「今動かないことで何を失うか」を数値で把握する視点を持ちましょう。
スモールステップで変化に慣れるマインドセットを作る
現状維持バイアスを外すためには、成功体験を積み上げる必要があります。
成功体験は最初から大きく積み上げるのではなく、少しずつ日々の業務で変化を実感してください。
Aという施策を1ヶ月試した結果、どのような成功が生まれたのかを実感することで徐々に現状維持バイアスが外れていきます。
このように現状維持バイアスはあらゆる方面から少しずつ変化を受け入れることで徐々に外れていくと考えてください。
経営における現状維持バイアスまとめ
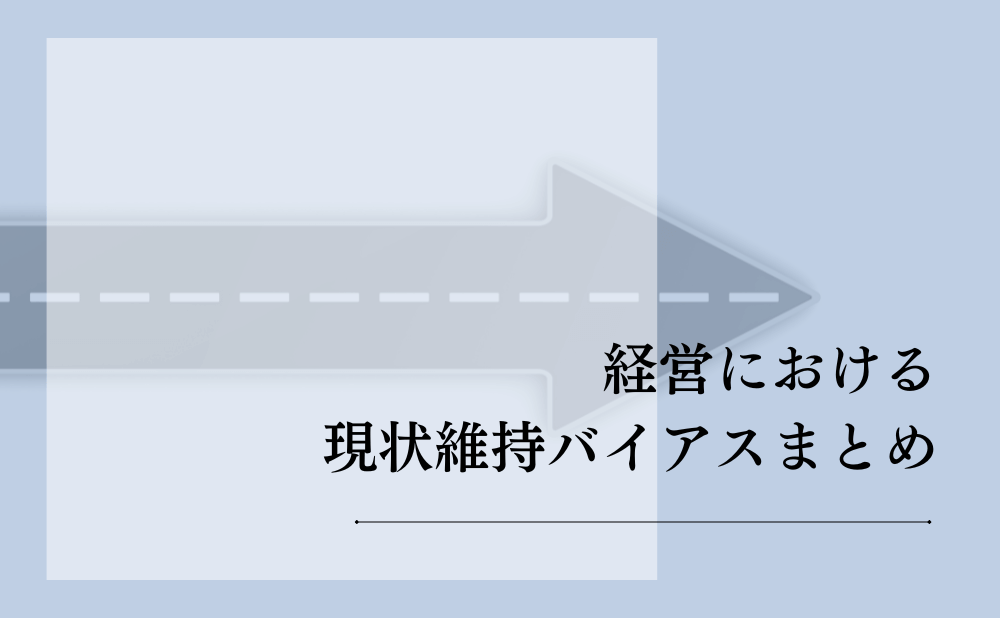
今回の記事では経営における現状維持バイアスを解説しました。
現状維持バイアスは経営に悪影響を及ぼす恐れがあるものの、徐々にしか外せないという性質もあります。
常に挑戦する精神を持ち、今の状況を受け入れるところから現状維持バイアスは外れていくと考えてください。
もし、あなたが集客上、現状維持バイアスが働いていると感じているのであれば、以下のページに挑戦へのヒントがあるので参考にしてみてください。
今回の記事が少しでも参考になったと思ったら、「いいね」で応援してもらえると嬉しいです!