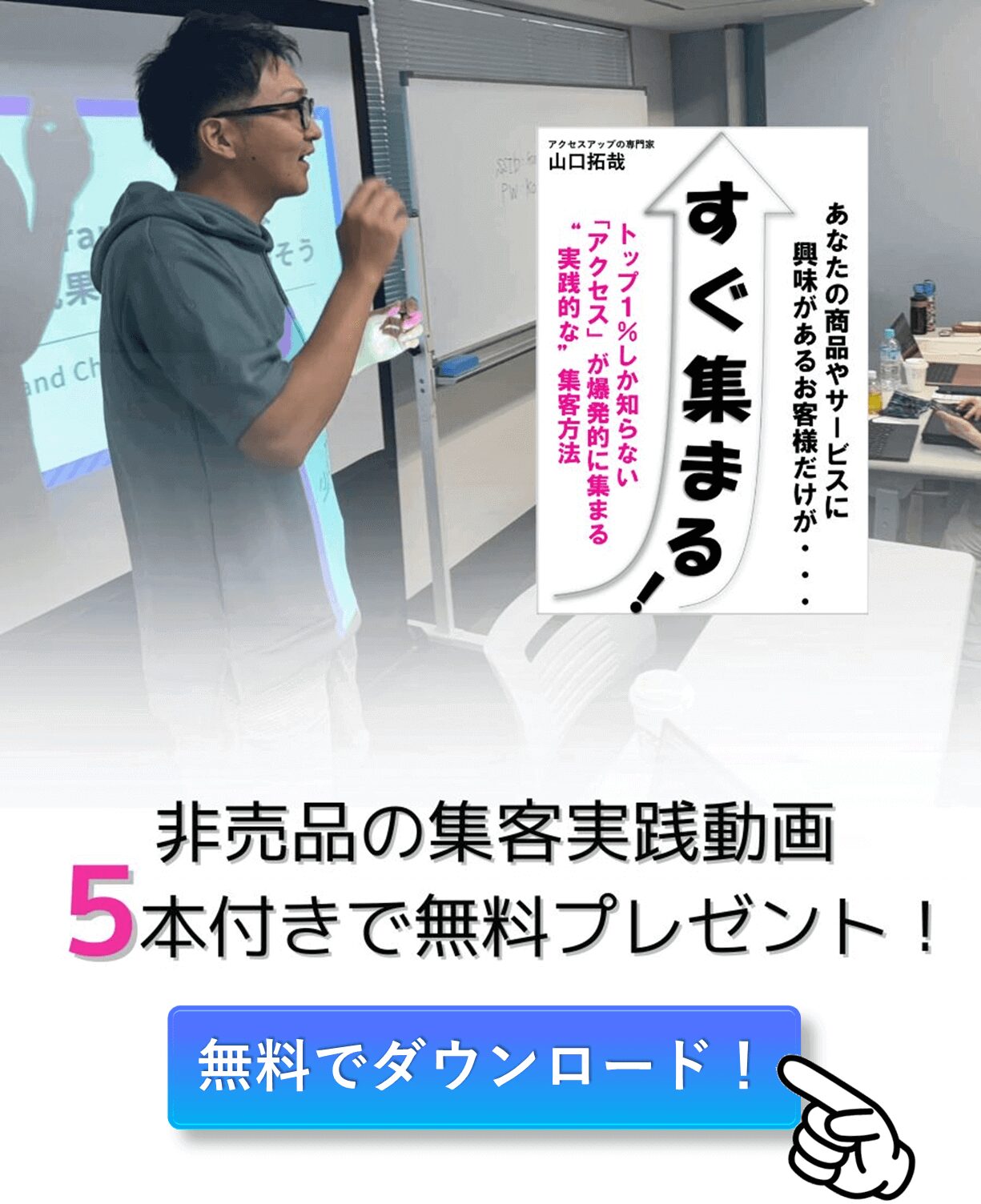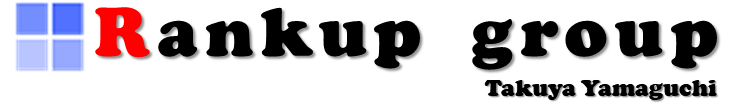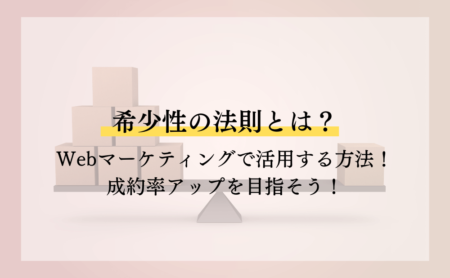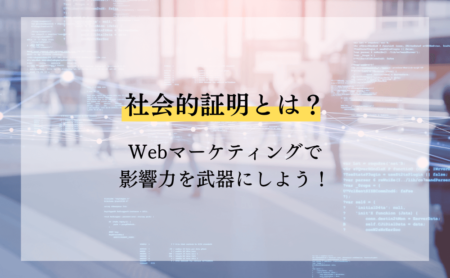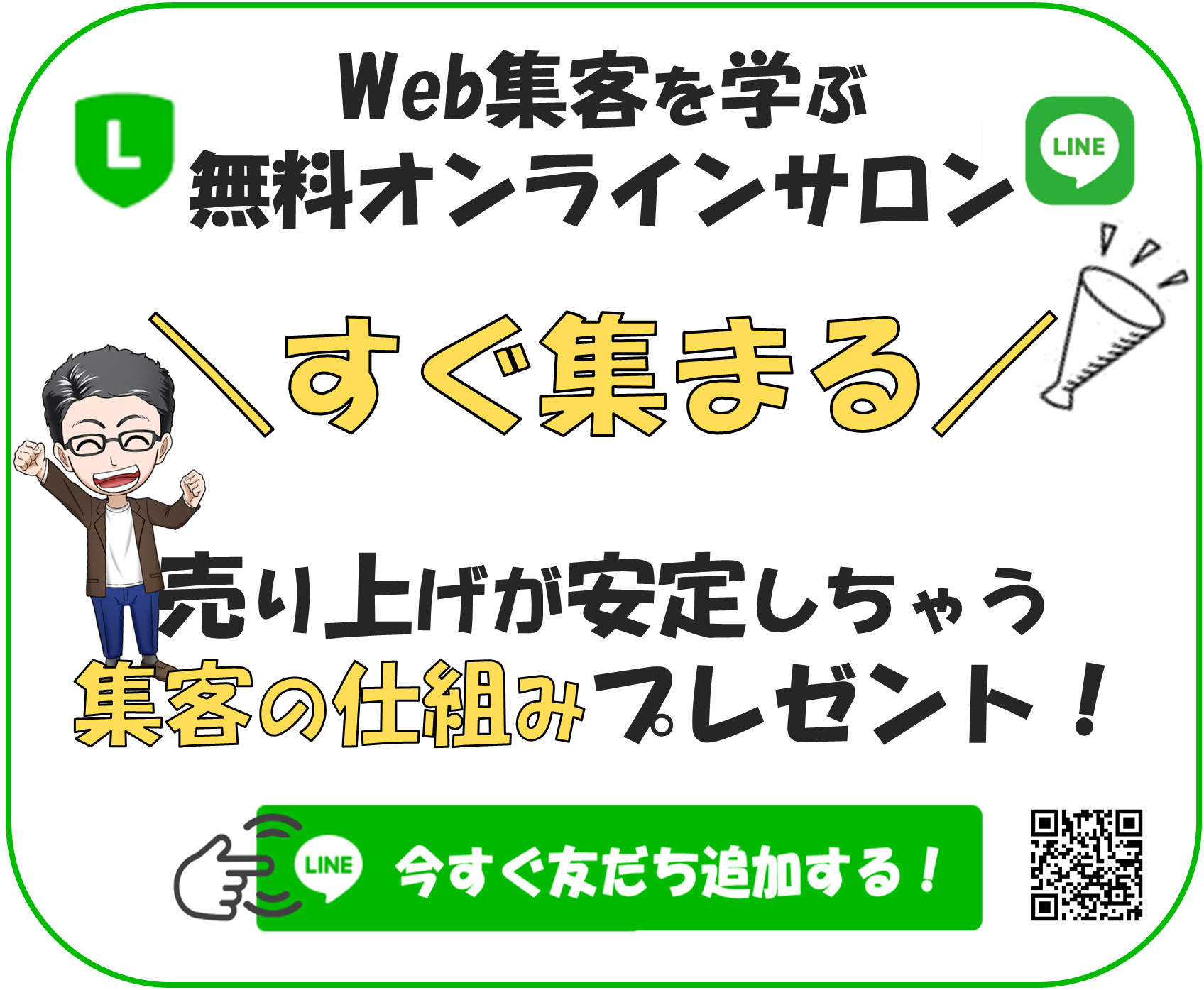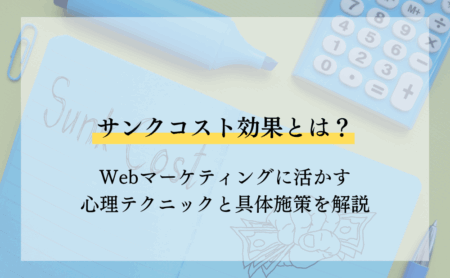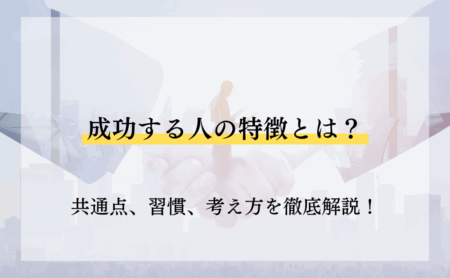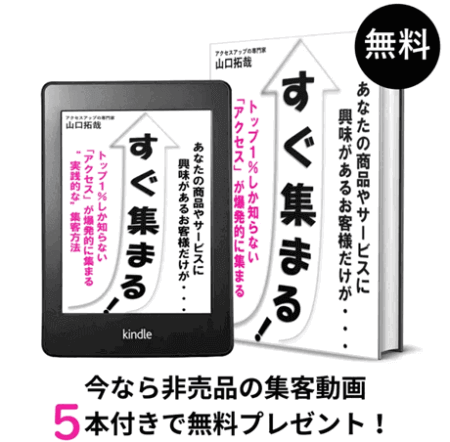限定合理性とは?Webマーケティングに活かすポイント
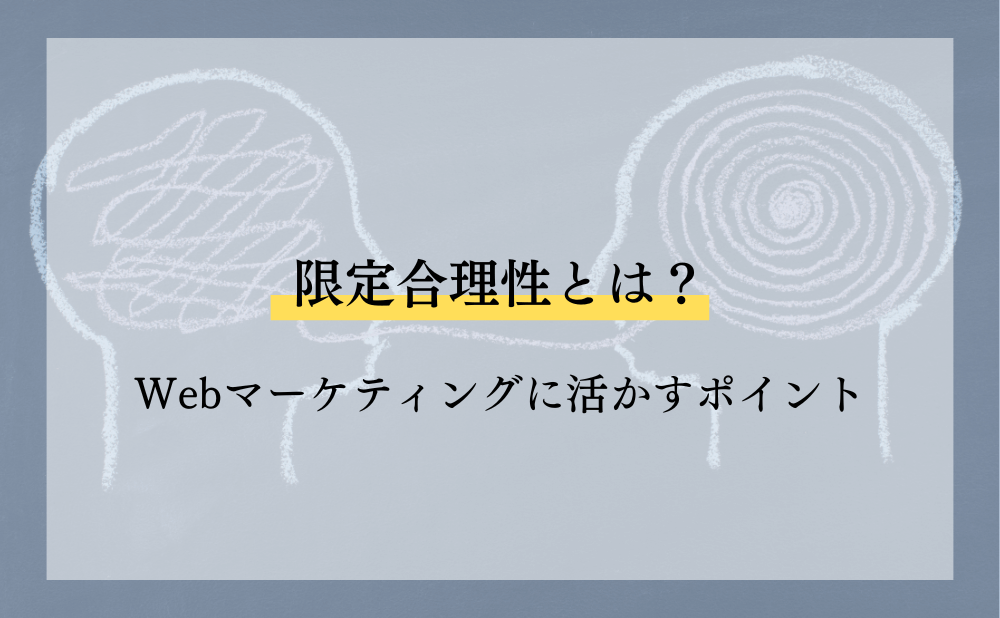
私たちは日々、様々な意思決定を行っています。しかし、そのすべてが論理的で完璧な選択とは限りません。
実は、人間の意思決定には「限定合理性」という特性が深く関わっています。この概念を理解し、Webマーケティングに応用することで、顧客の行動をより深く理解し、効果的な戦略を立てることができます。
この記事では、限定合理性の意味や具体例を分かりやすく解説するとともに、Webマーケティングでどう活かせるのかを実践的に紹介します。
- 限定合理性について理解したい方
- 限定合理性を活用してサイトのCVRを改善するためのヒントを探している方
- 限定合理性をWebマーケティングに活かす方法を知りたい方
限定合理性とは
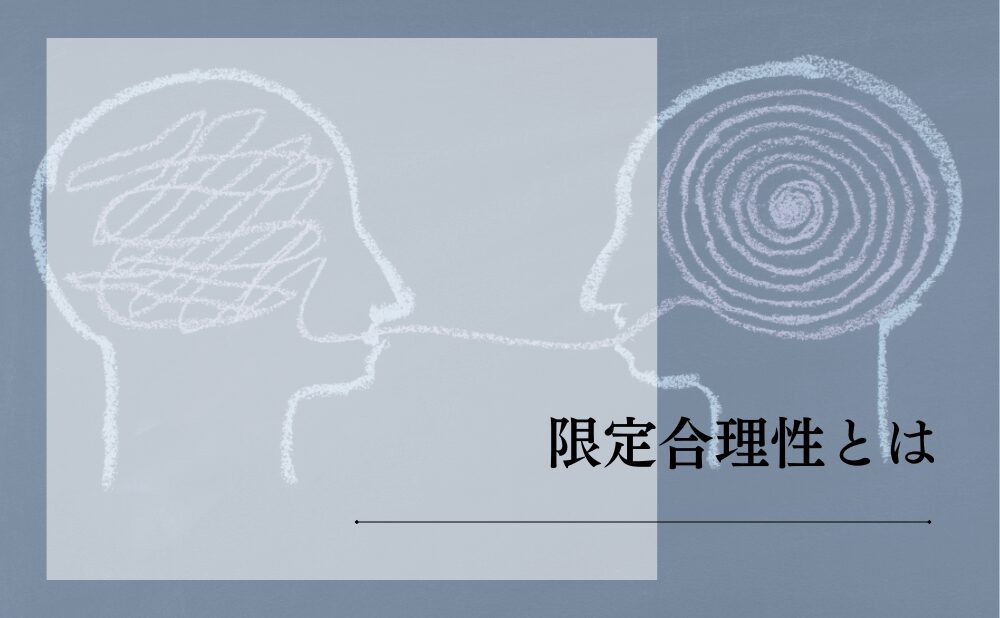
限定合理性とは、人が意思決定をする際に「すべての情報を正確に処理して最適な選択をすることができない」という前提に立った考え方・概念です。
限定合理性の提唱者と基本的な考え方
限定合理性は、アメリカの経済学者であり心理学者でもあるハーバート・サイモンによって提唱されました。
彼は、伝統的な経済学が前提とする「完全な合理性を持つ経済人(ホモ・エコノミクス)」のモデルに対し、現実の人間は常に全ての情報を収集・分析し、最善の選択を行うわけではないと指摘しました。
私たちは、入手可能な情報と処理能力の範囲内で、「満足できる」選択をしようとします。
Webマーケティングにも応用される限定合理性
限定合理性は、Webマーケティングでも意識しなければいけません。
というのも、ユーザーはすべての情報を熟考してからコンバージョン(問い合わせ・商品購入)するわけではなく、限られた時間や情報の中(限定的な要素)で「一度問い合わせしてみよう」と判断(合理化)しているケースが多いためです。
そのため、サイト構成や導線設計、CTAの文言においても、「ユーザーが最小の負荷で意思決定できるか」を常に意識する必要があります。
日常でもよく見かける身近な限定合理性

Webマーケティング以外で日常でよく見かける身近な限定合理性の一例は以下のとおりです。
- 就職活動
- スーパーでの買い物
- 経営判断
それぞれ解説します。
事例1.就職活動
大学生の就職活動では、数ある企業の中から志望する業界や分野の数社に絞ってエントリーするのが一般的です。
学生は学業やアルバイトに追われる中、限られた情報(企業説明会、ネットの評判、就職サイトのレビューなど)で意思決定を行います。
また入社を決める動機には「この会社は有名だから」「(説明会や面接の)雰囲気がよさそう」といった印象や直感に頼る場面も多く、あらゆる情報から完全に合理的な自身の状況にあった企業を求めるより「自分が納得できるレベル」の選択にとどまる傾向があります。
事例2.スーパーでの買い物
日常の買い物でも、限定合理性が働いている場面が多くあります。
スーパーマーケットで、消費者はすべての商品の価格・成分・レビューを比較することなく、パッと目についた商品を手に取ります。
「以前買って良かった」「特売シールが貼ってあった」「陳列位置が目立っていた」などが購買理由になることも多く、完全な合理的判断ではありません。
仮に完全な合理的判断をするなら、少なくとも来店できる距離のスーパー全ての商品価格を調べ行動する必要があります。
しかし、現実では時間をかけて検討するよりも「それなりに満足できる選択」を素早くすることがほとんどのはずです。
事例3.経営判断
経営の現場では、膨大な情報と選択肢の中から限られた時間で決断を迫られる場面が多いです。
新規事業の立ち上げ、組織再編、価格戦略の変更など、どれも全体像を100%把握した上での決断は難しいはずです。
経営者は自身の経験や限られたデータをもとに「最適だと思える」選択を行います。
これらの事例のように人は限られたリソース(情報や時間)の中で判断し、行動しているため、Webマーケティングでも限定合理性をベースに施策を考えていく必要があります。
限定合理性をWebマーケティングに活かす方法
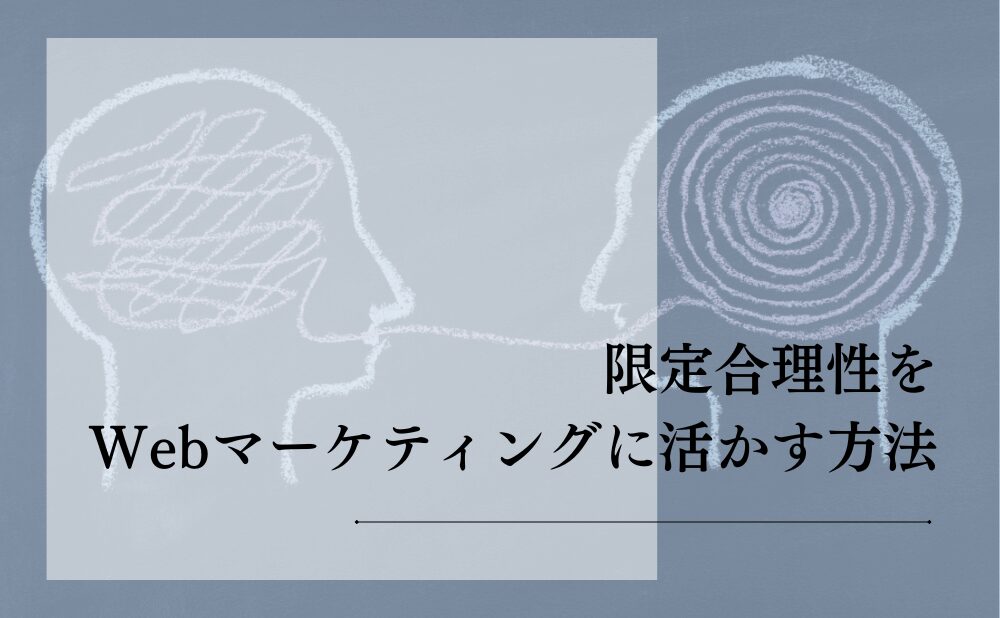
限定合理性をWebマーケティングに活かす方法の一例は以下のとおりです。
- 選択肢をシンプルにする
- 理解が難しいコンテンツをなくす
- 時間を浪費させないUI・UXの作成
- 意思決定を促す「心理トリガー」の活用
詳しく解説します。
選択肢をシンプルにする
ユーザーは限られた情報処理能力と時間の中で意思決定を行っているため選択肢が多すぎると「決められない」状態に陥りやすく、離脱に繋がるケースも多いです。
Webコンテンツでは商品のプラン数などを3つ以内に絞り、ひと目で比較できるレイアウトにすることが有効です。
また、「おすすめ」や「人気」などのラベル・バッジで選択肢に優先順位をつけると、判断のハードルを下げられます。
このようにWebマーケティングでは「選ばせすぎない」「分かりやすくする」ことが効果的です。
理解が難しいコンテンツをなくす
専門用語が多く、価格やサービス内容が複雑なコンテンツは、ユーザーにとって「理解しづらいもの」として処理されます。
ユーザーは調べなければ理解できない情報を調査することはほとんどなく、判断を回避してページを離れてしまいます。
- コンテンツA:図解や箇条書きが活用され、ユーザーが読みやすいコンテンツ
- コンテンツB:コンテンツAと同じ内容だが、全てテキストベース
仮に同じ内容のコンテンツがあったとしても、コンテンツAのほうが問い合わせ数はダントツに多くなるはずです。
テキストベースで粒度を細かく説明したとしても、「文章を読み込んで判断する」といった時間を使ってしまう行動はユーザーは嫌います。
反対に同じ内容でも図解や箇条書き、比較表を用いることで、ユーザーが少ない負荷で情報を受け取れます。
時間を浪費させないUI・UXの作成
ユーザーは自身の時間や注意力を無駄に消費することを嫌います。
ページの読み込みが遅い、必要な情報が見つからない、導線が複雑といったUX(ユーザー体験)の問題は判断放棄や離脱を招きます。
このようなUXがないようにするためには、ユーザーが求める情報に最短距離でアクセスできるようなUI(ユーザーインターフェース)設計が必要不可欠です。
ファーストビューに明確なCTAを置く、スクロールやクリック数を減らす、検索性を高めるなど、ユーザーの負荷を最小化する工夫が重要です。
これらのUI・UXの問題はヒートマップを活用し離脱率などを確認することで判断できるので、すぐに計測したい方は以下の記事を参考にしてみてください。

意思決定を促す「心理トリガー」の活用
限定合理性を持つユーザーの意思決定を後押しするために、様々な心理トリガーをWebコンテンツに散りばめることが有効です。
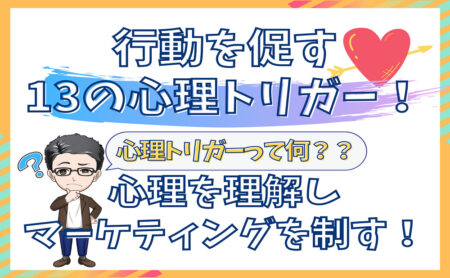
希少性の原理で緊急性を訴求
「限定100個」「残りわずか」「本日限り」といった表現は、ユーザーに「今買わないと損をする」という損失回避の心理を刺激し、緊急性を持たせます。
社会的証明で安心感を与える
「お客様の声」「導入事例」「販売数〇万個突破」「レビュー評価4.5」など、他の多くの人が支持していることを示す情報は、ユーザーに安心感を与え、購入へのハードルを下げます。
返報性の原理で価値を提供する
無料サンプル、無料eBook、お役立ち情報など、先に価値を提供することで、ユーザーは「お返しをしたい」という心理が働きやすくなります。
これが、メールアドレス登録や商品購入につながることもあります。
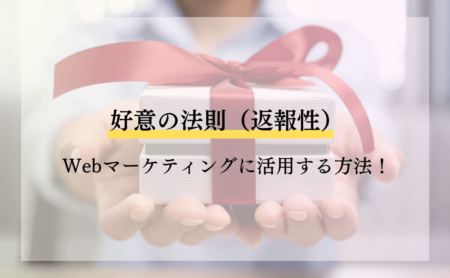
損失回避の法則で行動を促す
人は「得をすること」よりも「損をしないこと」を強く意識します。
「このセールを逃すと1万円損します」といった表現で、損失への恐怖を煽ることで、行動を促すことができます。

アンカリング効果で価格の魅力を高める
通常価格を大きく表示した上で、割引後の価格を提示することで、割引後価格がお得であるという印象を強く与えることができます。
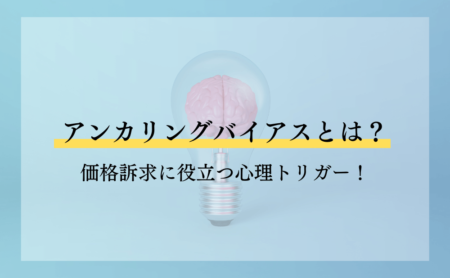
限定合理性をWebマーケティングに活用する際によくある質問

限定合理性をWebマーケティングに活用する際によくある質問の一例は以下のとおりです。
- 限定合理性をうまく活用できた事例を教えてください
- どのような施策で限定合理性を活用できますか
回答します。
限定合理性をうまく活用できた事例を教えてください
あるパーソナルトレーニングジムでは、問い合わせ導線を公式LINEに統一したことで、体験者数を増加させました。
要因としては、フォーム入力による手間を削減し時間の制約を軽くしたことです。
一般的にEFO(問い合わせフォーム最適化)と呼ばれる方法ですが、基本的にはユーザー側の負担の軽減をベースにしています。
どのような施策で限定合理性を活用できますか
限定合理性を活用できるWeb施策は次のとおりです。
| 施策内容 | 期待できる効果 |
|---|---|
| CTAボタンの文言を明確にする(例:「無料ではじめる」「3分で完了」) | 直感的にメリットが伝わり、クリック率やCV率の向上が見込める |
| 入力フォームを分割し段階表示にする | 決断疲れや離脱を防ぎ、途中で諦めるユーザーを減らせる |
| ナビゲーションに「人気」「おすすめ」などのラベルを付ける | 選択肢の優先順位が明確になり、迷いを軽減してスムーズな意思決定を促進できる |
| 難解な専門用語を避け、図や表を用いた簡潔な説明にする | 負荷を軽減し、理解と納得を促進する |
| ファーストビューに明確な行動導線を設置する | ページ滞在初期の離脱を防ぎ、意思決定への最短導線を提供できる |
限定合理性まとめ
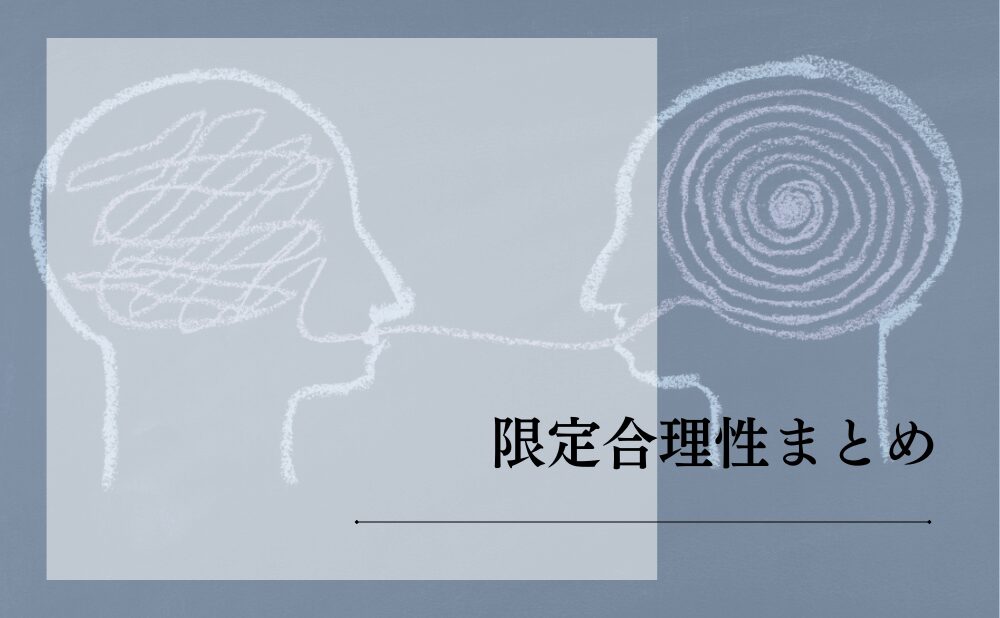
ユーザーはすべての情報を比較検討して最適な判断をしているわけではなく、「制約の中で妥当な判断」をしていることがほとんどです。
Webマーケティングでは、今回紹介した限定合理性を理解し、情報の出し方や選択肢の提示方法を工夫することで、成果につながる設計が可能になります。
限定合理性の考え方は広告運用でも活用できるため、以下のページで成功事例を確認するとともに、自身のコンテンツの立ち上げの改善に役立ててください。
今回の記事が少しでも参考になったと思ったら、「いいね」で応援してもらえると嬉しいです!