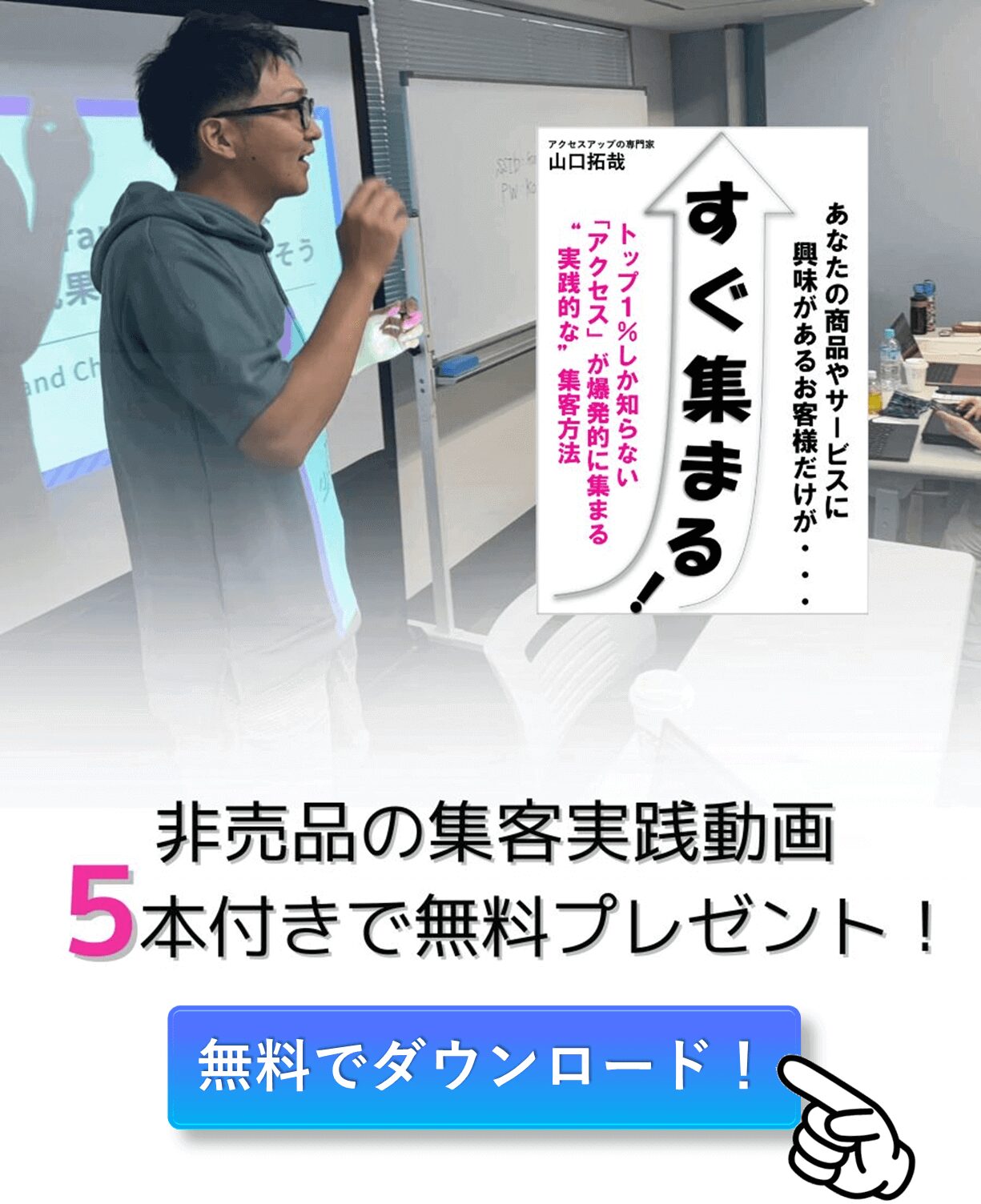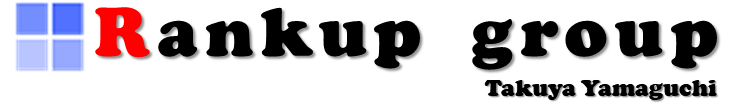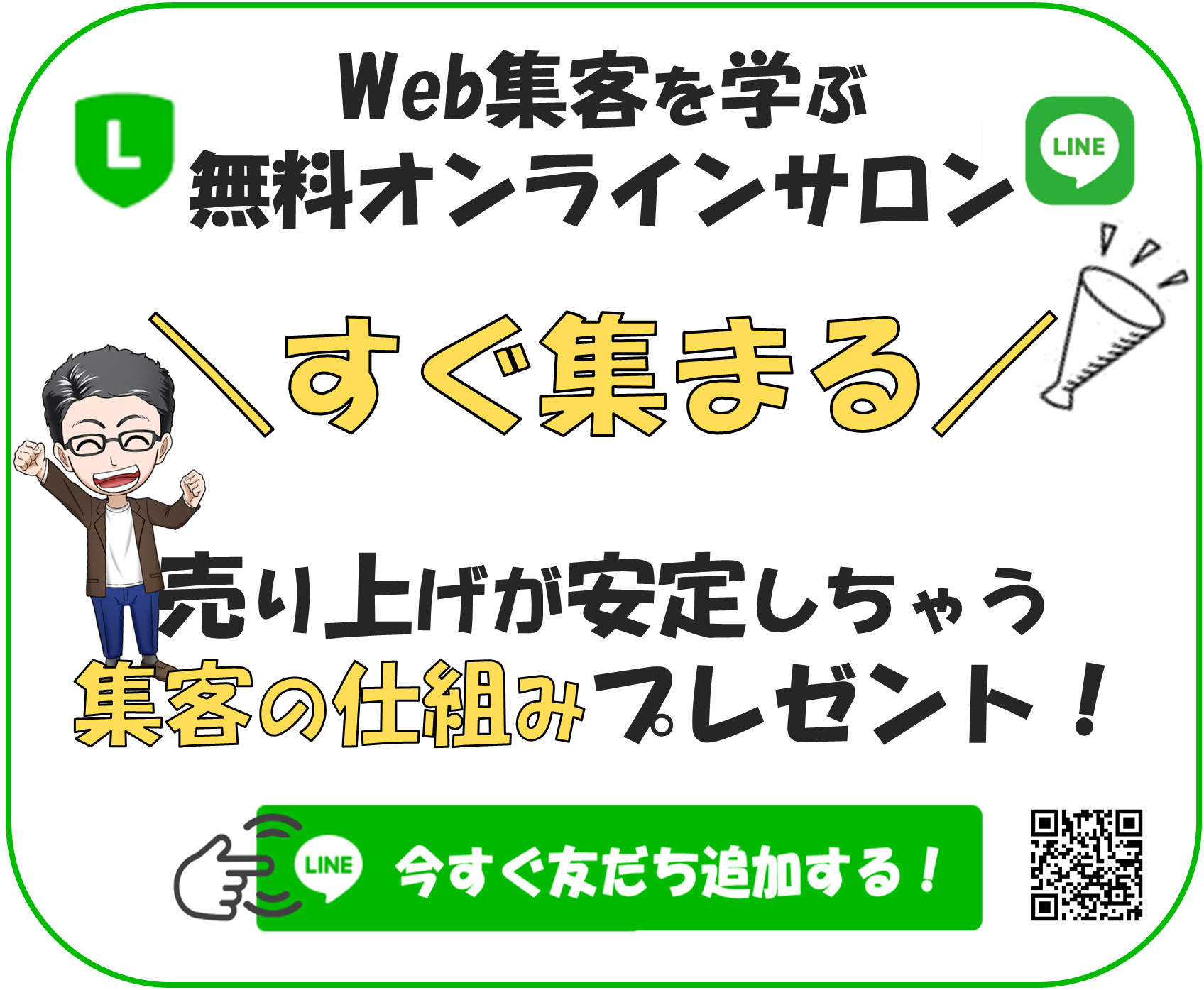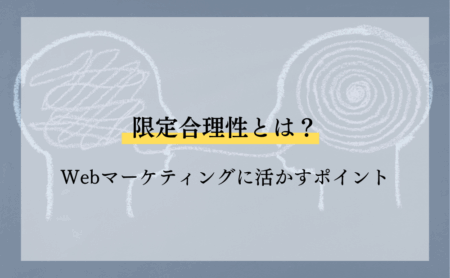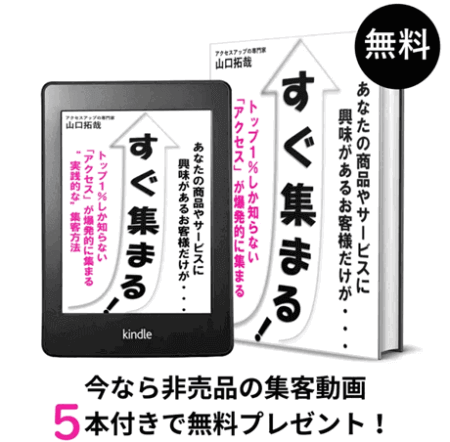サンクコスト効果とは?Webマーケティングに活かす心理テクニックと具体施策を解説
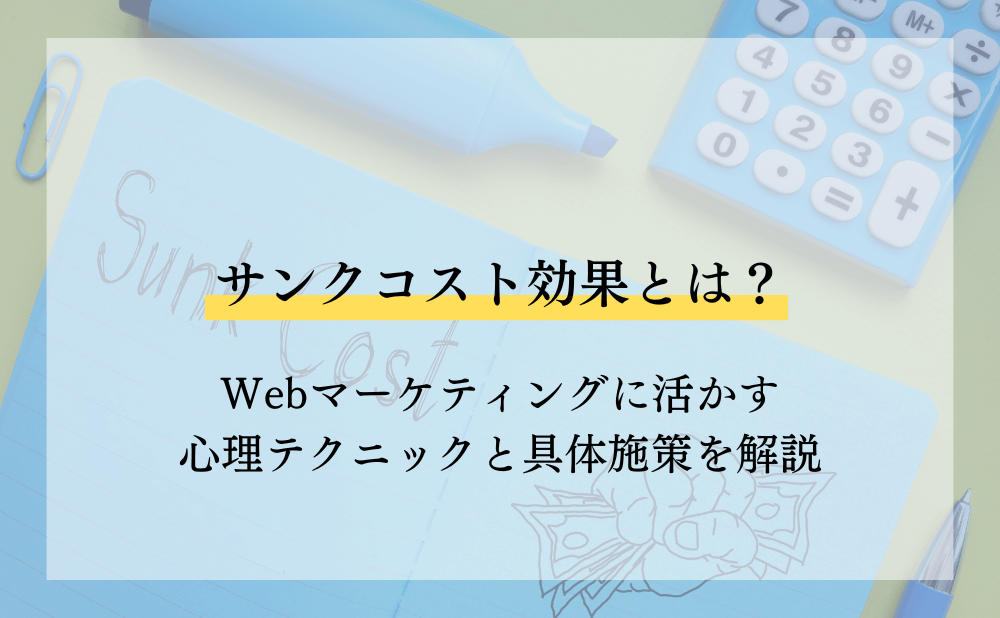
サンクコストとはどのような「心理状態」なのかと疑問に感じている方も多いはずです。
当記事では、サンクコストをWebマーケティングに活用する方法や、他の心理トリガーとの違いなどを含め、網羅的に解説します。
サンクコストは、他の心理トリガーと併用することで大きな反応を得られる「人の心の動き」なので、ぜひ参考にしてください。
- >>まずサンクコストとは何かを学びたい方
サンクコストとはへ - >>サンクコストをWebマーケティングに活用する方法を知りたい方
サンクコストをWebマーケティングに活用する方法へ - >>サンクコストが活かされている実例を知りたい方
Webマーケティングにおけるサンクコストが働いている実例へ
サンクコストとは
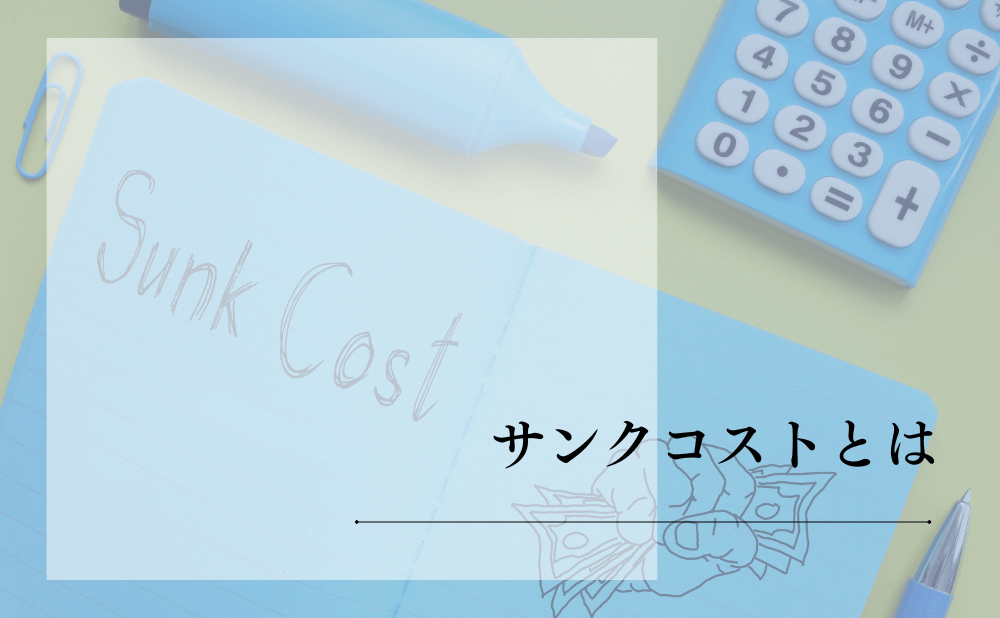
サンクコストとは、すでに投資してしまった「時間・お金・労力」といったコストのことを指します。
これらのコストは取り戻すことができないにもかかわらず、多くの人が「ここまで投資したのだからやめたらもったいない」と感じ、非合理的な行動を選んでしまう傾向があります。
この人間心理はビジネスにおいてもしばしば見られ、特にWebマーケティングの設計においても強力な武器になるため、Web施策の一環として活用してみましょう。
ただし、あくまで良い商品・サービスを購入してもらうための仕組みであるため、悪用は厳禁です。
コンコルド効果やプロスペクト理論との違い
サンクコストには他にも似たような心理トリガーがあり、違いを知っておくことでWebマーケティング上の施策にも違いを出せます。
以下の心理トリガーがサンクコストと似ているので、参考にしてみてください。
- コンコルド効果
- プロスペクト理論
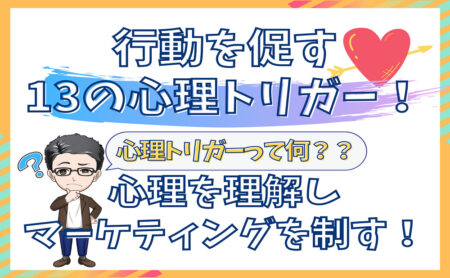
コンコルド効果
コンコルド効果は、巨額の投資を行った後に、明らかに損失が出るとわかっていても「ここまで来たのだから」と撤退できない心理トリガーです。
サンクコストは今までの投資に対しての心理トリガーですが、コンコルド効果は「投資額」による心理トリガーという違いがあります。
プロスペクト理論
プロスペクト理論は、人は「得をすること」よりも「損をしないこと」に強く反応するという心理です。
サンクコストが影響している場面では、この損失回避バイアスも絡み合い、行動を継続してしまいがちになります。

サンクコストをWebマーケティングに活用する方法
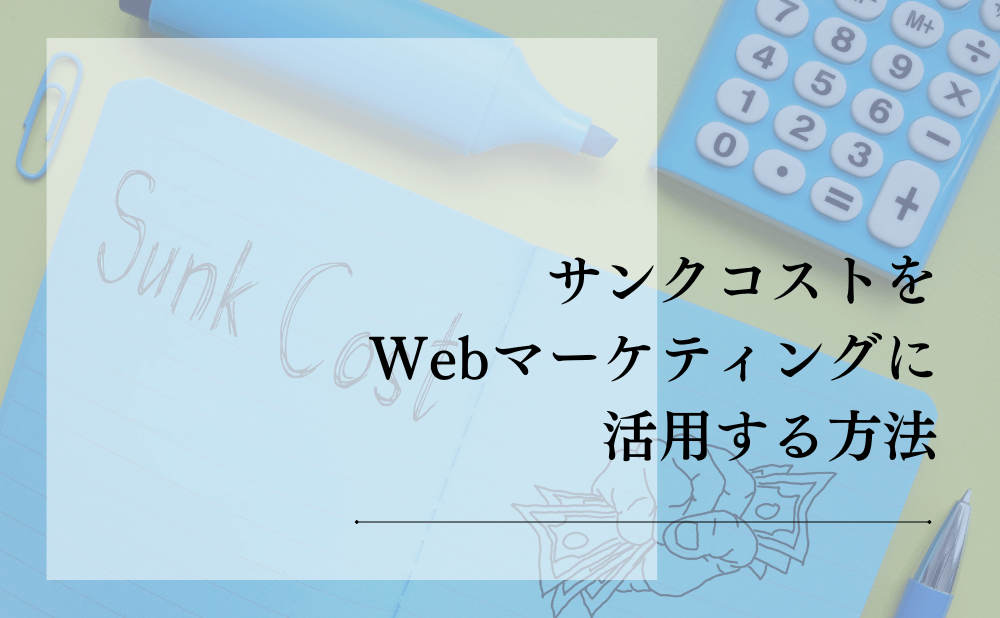
サンクコストをWebマーケティングに活用する方法の一例をご紹介します。
- コンテンツの長さや量を確保する
- 体験や相談会などを活用し、時間や労力を使ってもらう
- サブスクリプションモデルを導入する
それぞれ解説します。
コンテンツの長さや量を確保する
ユーザーが時間をかけて読んでいる記事や動画に対しては、「途中で離脱したらもったいない」という心理が働きます。
ボリュームのあるホワイトペーパーや無料eBook、読み応えのある記事コンテンツなどは、自然とサンクコスト効果を生み出す仕掛けになります。
読み応えのあるコンテンツを揃え、最後まで読みたいという反応を得るためには、セールスレターの書き方なども学ぶ必要があるので、気になる方は以下の記事を見てみてください。
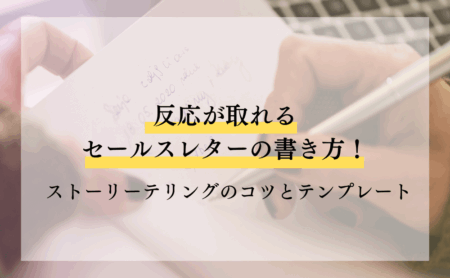
体験や相談会などを活用し、時間や労力を使ってもらう
無料体験、個別相談、診断コンテンツなどを提供することで、ユーザーに「労力」や「時間」を使ってもらいます。
時間や労力を事前に使ってもらうとユーザーは「せっかくここまでやったのだから続けよう」と考えやすくなり、CVR(コンバージョン率)1向上にもつながります。
ただ、近年では「無料体験、個別相談」などは一般的になってきており、ユーザー側が労力と捉えない傾向もあるので、「ユーザーが実際に体験・実施するコンテンツ」を用意していきましょう。
WebサイトやLPなどで訪問者が目標とするアクション(購入・問い合わせ・登録など)を実際に行った割合を示す指標。
サブスクリプションモデルを導入する
一度契約・登録すると「継続しないともったいない」というサンクコストが働きやすいのがサブスクリプションです。
NetflixやAmazonPrimeのようなサブスクリプションを個人や中小企業で行うことは難しいので、月額契約のコンサルティングなどでまずは代用してみてください。
その際には月1回の面談などを行い、お客様の要望の変化などを常に把握し、満足度を高めるように動くと継続率が上がります。
Webマーケティングにおけるサンクコストが働いている実例
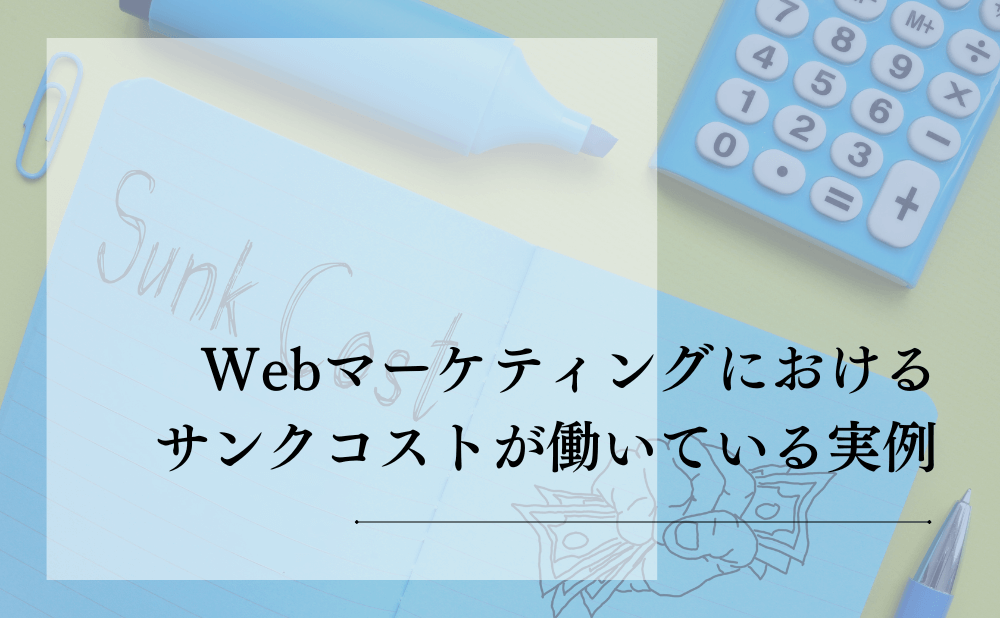
Webマーケティングにおいて、サンクコストが働いた実例をいくつか紹介します。
- 学習アプリの継続利用
- 無料カウンセリング付きのジム入会
- メルマガ登録からの限定オファー
詳しく解説します。
サンクコスト事例1:学習アプリの継続利用
語学学習アプリや資格学習アプリでは、「連続○日達成」や「皆勤バッジ」などのゲーム要素を導入しており、ユーザーが継続する理由の一部にサンクコストが働いています。
たとえば、10日連続で学習を続けたユーザーは、「ここで止めたら今までの努力が無駄になる」というサンクコストから、翌日も学習を続けやすくなります。
サンクコスト事例2:無料カウンセリング付きのジム入会
多くのパーソナルジムでは、入会前に無料カウンセリングやトレーニング体験を行っています。
この無料施策は単なるサービスではなく、時間とエネルギーを使ってもらうことで、「ここまで来たのに入会しないのは損だ」というサンクコストを働かせるマーケティング施策です。
ジムや学習塾、コンサルティングなどは基本的に無料体験を通して入会してもらいますが、サンクコストばかりだけではなく、無料体験でも感じられる「圧倒的価値」を提供すると入会率が上がります。
サンクコスト事例3:メールマガジン登録からの限定オファー
メールマガジン登録やLINE登録後に段階的に情報提供し、最終的に限定キャンペーンへと誘導する設計をすることで、サンクコストが働き商品・サービスの購入率が向上します。
たとえば、LINE公式に登録した後に長編の価値ある動画を提供し、その中に限定オファーを組み込むというマーケティング施策もあります。
このような方法を活用することで、サンクコストがうまく活用され商品・サービスの購入率が向上します。
他の心理トリガーと組み合わせてサンクコスト効果を最大化する
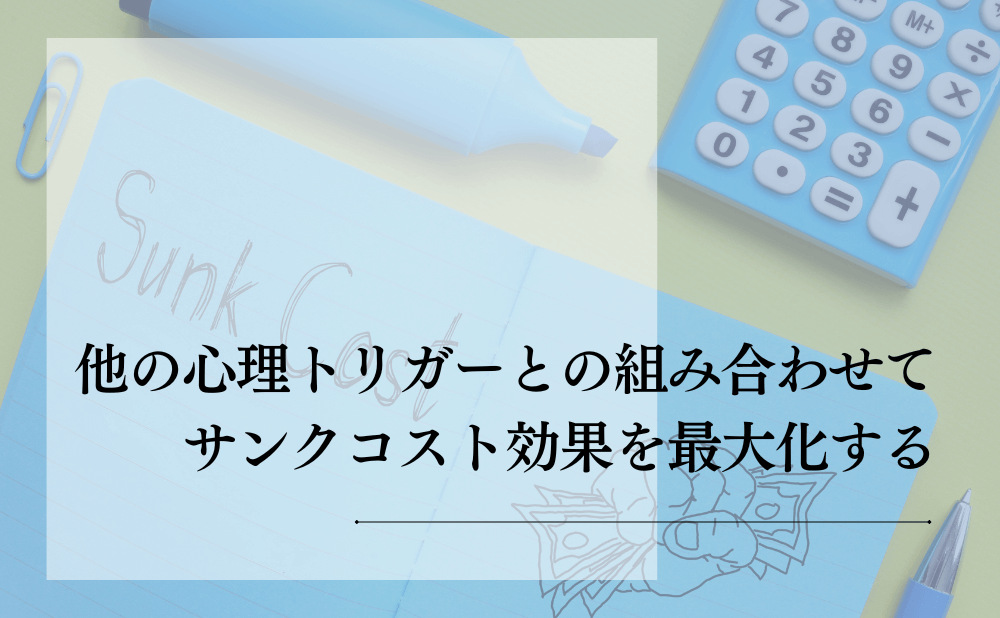
サンクコストの効果を最大化するためには、次のような心理トリガーと方法を組み合わせてみることをおすすめします。
- バンドワゴン効果と組み合わせた「みんな始めてる」演出
- フレーミング効果との組み合わせで損失感を演出
- 希少性(スノッブ効果)と組み合わせて「離脱のデメリット」を強調
それぞれの詳しい解説を行います。
バンドワゴン効果と組み合わせた「みんな始めてる」演出
バンドワゴン効果とは、「多くの人がやっているから自分もやろう」とする心理です。
サンクコストと組み合わせることで、より強い動機づけになります。
活用例としては以下のような方法があります。
- 動画再生中に「このセミナー、既に5,000人が受講済み」と表示。
>> ユーザーは「ここまで見たし、多くの人が見ているなら自分も続けよう」と感じる。
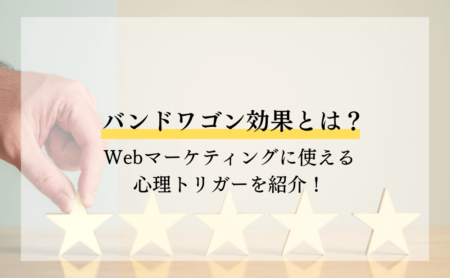
希少性(スノッブ効果)と組み合わせて「離脱のデメリット」を強調
スノッブ効果は「他と違う」「限られている」ことに価値を感じる心理トリガーです。
スノッブ効果とサンクコストを掛け合わせることで「この機会を逃すのは損」という印象を強めます。
また損失を回避するプロスペクト理論も働き、人の心理を変化させられる可能性が高まります。
活用例の一例は次のとおりです。
- 「この動画は今週だけ公開」「一度離れると再視聴はできません」
- 「今だけのご案内。継続申込がない場合は特典が消滅します」とコピーを書く
>>「この動画は今週だけ公開」の場合、今週だけ公開という希少性と、動画を見たというサンクコストが働きます。
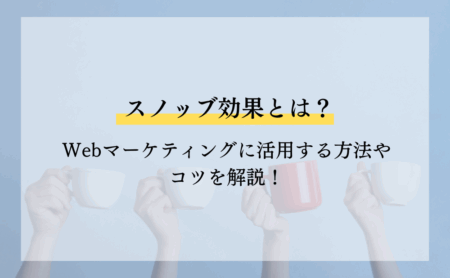
サンクコストまとめ
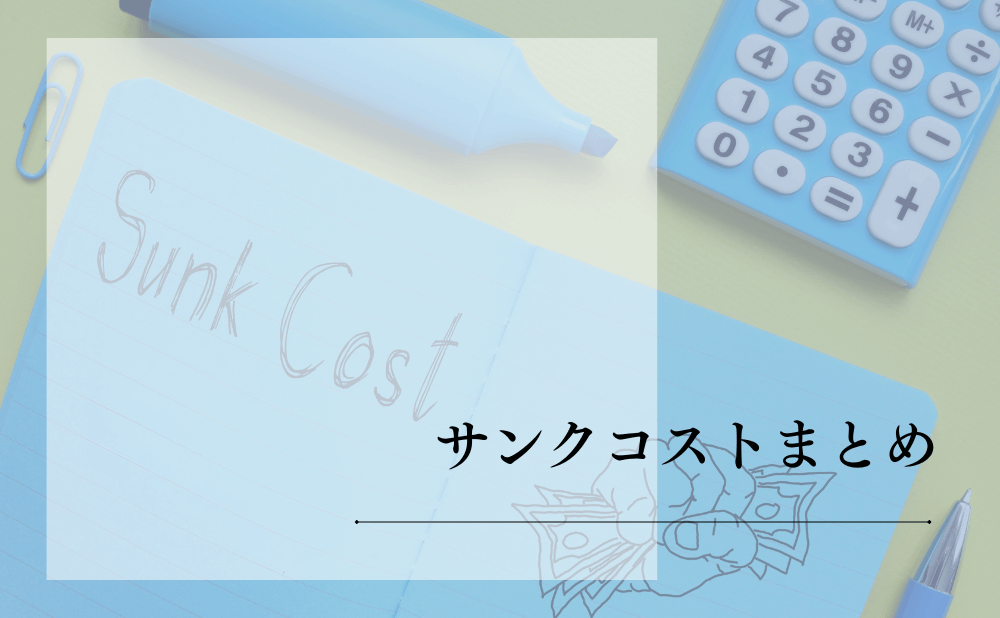
サンクコスト効果は、ユーザーの「ここまで投資した損失を回避したい」という心理の動きをマーケティングに活かす強力な心理トリガーです。
体験・コンテンツ・サブスクリプションなど、ユーザーの時間や関与を促す施策とサンクコストは相性が良く、LTV2の向上やCVR改善(入会率や購入率)に直結します。
1人の顧客が企業にもたらす総収益を示す指標。
長期的な収益性やマーケティング戦略の最適化に役立ちます。
とはいえ、サンクコストの心理トリガーは悪い商品・サービスでもうまく活用すれば反応を獲得できる強力な心理トリガーです。
そのため、誠実さをもって必ず商品・サービスを提供し、お客様の満足度が高い状態にすることも目標の1つとして組み込んでください。
心理効果を用いたWebマーケティングを学びたい方は、以下のページから無料動画を確認してみてください。
今回の記事が少しでも参考になったと思ったら、「いいね」で応援してもらえると嬉しいです!